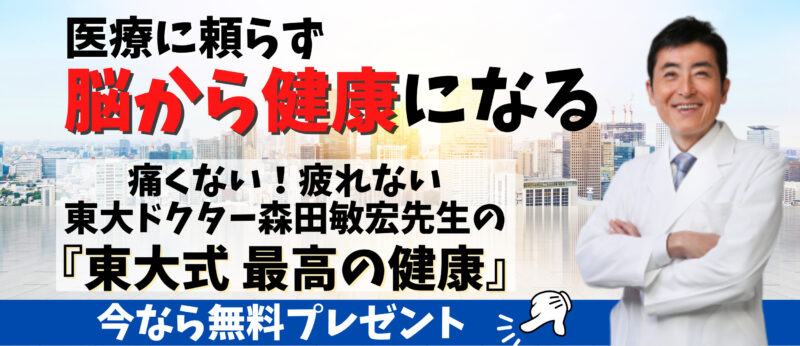先日このような本を読みました。
タイトルは『道路を渡れない老人たち』です。
帯にも、
- その時が来てからでは手遅れ
- リハビリ難民 200万人を見捨てる日本
- 寝たきり老人はこうして作られる
とショッキングなタイトルそして帯なのです。
そこで今日は、老後貯筋問題を考える!道路を渡れない老人たちという話をしたいと思います。
高齢者は道路を渡れない!?
道路を渡れないとはどういうことでしょうか?
青信号の間に道路を渡りきるためには、秒速1メートル以上で歩く必要があります。
つまり、1秒ごとに1メートル以上進まなければならないということです。
ところが、この本の著者はリハビリ専門のデイサービスを経営しており、そこで利用者の歩行速度を調べた結果、平均の歩行速度が秒速0.58メートルであることがわかりました。
必要な速度である1メートルには届かないのです。
さらに、秒速0.9メートル以上の速度が出せた人は144人だけでした。
秒速0.9メートルでもギリギリで、渡りきれるかどうか分からない状態です。
この中で青信号の間に確実に道路を渡れるのは、わずか3人に1人か、それ以下の割合に過ぎません。
推計では、青信号の間に道路を渡りきれない高齢者が、日本には300万人以上いるとされています。
そのため、このような方々は買い物に行くことすら困難であり、「介護難民」と言える状況に置かれています。
この本の著者は、日本のリハビリテーションや医療、介護には多くの課題があると主張しています。
この現実は、社会全体で考えるべき重要な問題を投げかけているのです。
それを支持するデータとして、高齢者の寝たきり率が、
- 日本はなんと40.9%
- アメリカは欧米では比較的高くて6.5%
- デンマークは4.5%
- スウェーデンは4.2%
このように日本の寝たきり率が圧倒的に多いところからも医療とか介護の問題であると述べているわけです。
しかし、本当に医療や介護が悪いから、速く歩けない人が増えたり、寝たきりが増えてしまっているのでしょうか?
老後に早く歩けなくなるのは医療や介護のせい?
ちょっと私の考えは少し異なります。
私の意見としては、これは医療や介護のせいではないと考えています。
まず、リハビリとか介護という言葉(用語)の意味について、もう一度確認してみたいと思います。
リハビリというのはrehabilitation(リハビリテーション)の略です。
rehabilitationの
- 「re」は「再び」という意味です。
- 「habilitate」は「適した状態にする」という意味です。
ですから、直訳すると「再び適合させる」
例えば、交通事故や骨折などで歩けなくなったけれど、訓練をして元通りに歩けるようにする。
そういった意味合いがリハビリテーションになります。
介護というのは、「身体や精神が健全でない状態にある人の行為を助ける世話」という意味になります。
少しわかりにくいので、あとで2つの図を書いて説明していきたいと思います。
介護の区分というのがあります。
要支援1は、居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする状態です。
自分で身の回りのことができなくなっている要支援状態なわけです。
そこまでいってしまってからでは、全く手遅れというわけではないのですが、ちょっと遅いわけです。
これらを図で表すとどういうことになるか?
ベースライン(元の状態)が、矢印だとします。
リハビリは、一度弱ってしまった状態から元々のベースラインの状態に戻そうとすることです。
それに対して介護とは、もうすでにある程度のベースライン(自分で自立して生活できる、横断歩道もちゃんと渡れる状態)よりもすでに下がってしまった状態です。
これは、放っておけばどんどんどんどん悪くなるわけです。
それに寄り添ってあげることによって、下がってしまったラインを少し緩やかにしていくくらいの意味合いです。
思いっきりベースラインまで引き戻すという意味ではありません。
少なくとも今の介護では、それは難しいからです。
ですから、医療や介護に高齢者が弱ってしまったことの責任を求めるのは少しおかしいのではないかと私は考えるわけです。
老後のために筋肉を「貯筋」!
これを別な観点から見てみたいと思います。
一時期、「老後 2000万円問題」というのが話題になりました。
2000万円で足りるのかという話もありますが、老後の蓄えとして2000万円必要という話題がでました。
これを「老後貯筋問題」に置き換えてみたいと思います。
老後に備えて、ある程度の貯金あるいは資産がないと困ってしまいますよということです。
では、貯金がないからといって国がサポートしてくれるかというと、そんなことはありません。
全くお金がなくなったら生活保護というシステムがありますけれども、そうではない場合そこまでのサポートはないわけですね。
最近、筋肉を貯めると書いて「貯筋」という言葉が流行っています。
この貯筋も、各自でやはり責任を持つ必要があるのではないかということです。
老後になって、
「筋肉が足らないですよ」
「足らないから国が何とかしてください」
と言っているのが、今の医療とか介護の状況なのです。
昔は筋力の維持が必要だとか、そういうことがわからなかったので、やむを得ないかもしれません。
しかし、今はそういった情報も十分に知られるようになっているわけです。
実際のところ特殊な病気以外は、貯筋(筋力を維持)することは可能です。
例えば特殊な病気とは、筋ジストロフィーといって筋肉がどんどん壊れる病気があります。
こういう病気の場合は貯筋は無理なのですが、特殊な病気ではない人は、貯筋することは十分可能です。
ですから、やはり貯筋を早い段階からやっておいた方がいいのではないかと思います。
そうすれば「老後貯筋問題」で困ることはなくなるわけなのです。
では、そのためにどうしたらいいか?
まず今の状態を把握する必要があります。
お金の場合、
- 今どれだけのお金があるのか
- どれだけの収入があるのか
それと同じように、
まず今の筋力の状態、体力の状態を把握する必要があります。
- 今どのぐらい足らないのか
- あるいはどのぐらい足りているのか
そこから、
「どのぐらい貯筋(筋トレ)しましょうという」
というプランを立てて実行していけばいいわけなのです。
手遅れになる前に貯金を!
もちろん、これは高齢の方が自分でやるのは少し難しいと思います。
しかし、専門のトレーナーとか理学療法士がつけば十分可能です。
これは歳をとってからやるよりも、なるべく早い段階からやったほうがいいです。
何もしないでいると私たちの筋肉は大体年間で1%減少していきますので、気付いた時には手遅れかかなり悪い状態になってしまいます。
そうなる前に、自分の状態を把握して貯筋を進めていかないと、気づいたときには、
- 貯筋問題に直面する
- もう道路が渡れなくなっている
ということになってしまうのです。
「そうならないうちに、実行していきましょう!」
というのが私のおすすめするやり方です。
他にも運動に関する記事はこちら
↓
ブレインヘルスでは、筋力を落とさない方法を学ぶことが出来ます。 ▼ ▼ ▼ ▼
東大ドクター 森田敏宏先生の『脳から健康になる7つの法則』プレゼント
痛くない!疲れない!
東大ドクター 森田敏宏先生の『東大式 最高の健康法』
『脳から健康になる7つの法則』(PDF版)を今なら無料プレゼント
お申し込みは今すぐこちらから!